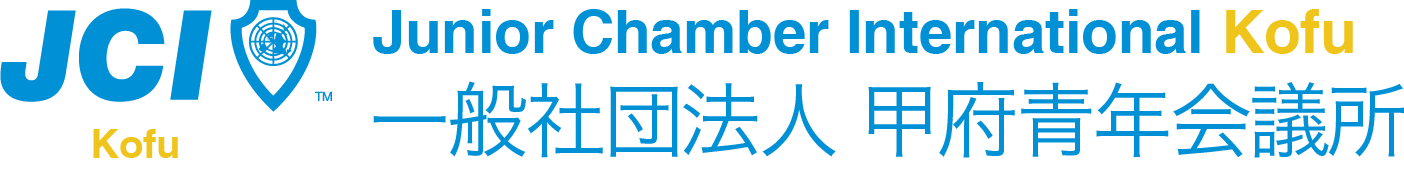一般社団法人甲府青年会議所
第72代理事長
大島 わかな

【はじめに】
スーツ姿の多くの人の胸にSDGsバッジが見られるようになりました。教育テレビでは「共 生マインド」を育む番組が作られました。貧困、健康、ジェンダー、環境など、様々な分野 における課題解決に関心を持ち、取り組んでいくサステナブルな社会、そしてこれを実現す るためのサステナブルな地域・組織が求められています。
そしてこの時代の転換に、新型コロナウイルスの感染拡大がさらに拍車をかけました。消 費の低迷、働き方の多様化といった課題が顕在化し、「企業の社会的使命」があらためて認 識されるようになりました。国際通貨基金(IMF)や経済協力開発機構(OECD)は「インク ルーシブ・グロース(包摂的成長)」を掲げ、取り残される人をなくし、包括的な成長を目 指すことを理念としました。
人々が手をとりあい社会課題を解決する社会。誰も取り残されず、平等に活躍できる社 会。このような社会を目指し、人々は、世の中で是と提唱されるものを積極的に取り入れよ うとしています。世の中に取り残されないように、持続可能であるように、時代の転換に追 従するかたちで必死に自身を変化させています。
この変化は重要であり必要なものです。私たち甲府青年会議所も、このコロナ禍で様々な 変化を遂げました。WEB会議システムの導入や、例会・事業のWEB参加を可能にしたことは、 コロナ禍はもとより様々な事情によりその時その場所に集合することが困難な会員の参加を 可能にしました。さらに会議資料のWEB上での共有は、離れていてもリアルタイムで同一の
資料を共有し、手を加えていくことを可能にしました。これらが組織にとって非常に歴史的 で画期的な変化であったことは言うまでもありません。まだまだ変えられるものはありま す。引き続き、時代に則した手法を取り入れ、より良い組織を目指していくことが必要で す。
しかし、このような世の中の変化の多くは、あくまでも土台作りに過ぎません。誰も取り 残されない社会はゴールではなく、むしろ新たなスタートに過ぎないのです。私たち甲府青 年会議所が目指すべき「明るい豊かな社会」はその先にあります。
私たちが「山の都」と称する活動エリアである甲府市、甲斐市、中央市、昭和町は、山梨 県の中枢といえる地域です。それぞれの自治体がそれぞれの地域の特性を活かした発展を遂 げています。しかし、地域全体としてみると少子高齢化や人口減少という深刻な課題を抱え ています。2023年においてもいまだ解決策を見いだせていない状況です。これに伴い、事業 承継者やコミュニティの担い手の減少により維持継続が困難となっている企業・組織も依然 として多く存在しています。さらに、コロナ禍による打撃は継続しており、地域経済は疲弊 しています。観光産業では、富士山という地域資源の恩恵や、信玄公祭りという大規模イベ ントによる一過性の影響はあるものの、山の都全体をみたときにそれ独自で観光客を強く誘 致するような継続的なものは少ないと言わざるを得ません。大型ショッピング施設は休日多くの買い物客で賑わっていますが、地域の独自性は乏しく、県内産業の衰退が危ぶまれてい る状態です。
さらに、新たな生活様式が浸透し、人と人との接触が何となくタブーと感じられてしまう この時代。遠出もしづらく、海外に行くことも難しい状況が続いています。接触の方法につ いても、自然と「対面でなくてもよい」という意識が形成され、対面での接触ができる機会 にあってもあえてリモートでの接触を選択する人が増えました。人間が本来持つ社会的な交 流の機会が失われています。その弊害は計り知れません。
このような時代だからしょうがないと、閉鎖的な時間を過ごしていいのでしょうか。良い と言われることだけをやり、それで満足をしていいのでしょうか。私も、皆さんも、皆さん の大事な家族も、人生は一度きりしかないのに、流れに身を任せて今を生きるだけでいいの でしょうか。
私はこの地域が大好きです。山々や渓谷などの豊かな自然、武田信玄に代表される歴史、 祭りや芸能などの多彩な文化、宝飾やワイン、温泉などの地域に根ざした産業。これら良い ものをもっと取り上げて発信し、この地域の魅力を県内外の多くの人に知ってもらい、呼び 寄せ、この地域を発展させたい。この地域を愛する皆さんも同じ気持ちだと信じています。
人と人との関わりの機会も諦めたくありません。特に子ども達の成長を考えたときに、一 方的な情報発信ではなく、情報や意見を交換し共感する喜びを感じてもらいたい。そのため に、子ども同士の交流、大人との交流、異文化との交流など、交流の機会を積極的に作って いくことが必要であると考えています。
こんな時代だからこそ、山の都としての独自性を活かすとともに、アフターコロナを見据 え、人のにぎわいを作り出せるような積極的な施策の構築が求められています。それが今、 山の都において求められている甲府青年会議所の役割であると信じ、私たちは未来を見据え てこの地域に仕掛けていきます。
【湧き上がれ、地域の魅力】
この山の都には多くの地域資源がありますが、それ独自で日本中に知られ、また観光客を 強く誘致するようなブランディングは成功していません。この地域のまちづくりにおいて は、「〇〇のまち」というように、何か一つを取り上げて一点集中でプロデュースしていく 力強い動きが求められています。
この地域の誇れる魅力を考えたときに、多くの人が真っ先に思い浮かべるのは「豊かな自 然」なのではないかと思います。たとえば三市一町各地に湧き出る多様で上質な温泉、山々 や渓谷、滝、湖といった自然豊かな景勝地等、自然豊かな環境とそこから生まれる地域資源 は私たちの住み暮らす地域の魅力であり誇りです。この魅力を活かし、三市一町をつなぐ横 断的なシステムを作ることができれば、それは地域住民にとっても、また観光客にとっても、山の都を堪能していただける絶好のツールとなり、三市一町全体の活性化につなげてい くことができます。
まちづくりという一朝一夕には成しえない大義をなすにあたっての私たちの役割、そのイ メージはまさにトリガーです。私たちが行うことは、まずは誰よりもテーマとする地域資源 について学ぶこと。とことん学び、誰よりも魅力を知り、実感することです。その上で、同 様の魅力を持つ地域との差異、ブランディングしていくための新たな視点、取り上げること による地域への波及効果などを十分検討し、施策を構築し、その施策を地域の行政、住民、 各種団体・企業に提案し、賛同者をつなげ、共に実現し、そして引き継いでいく。単年度制の組織であることの限界を越え、地域への定着まで見据えて動いていくことが必要であると 考えています。
地域の良いものを戦略的に取り上げて発信することで、興味をわかせ、話題を作り、人 をこの地域に呼び寄せる。そのようにしてこの地域を、地域の誇りとにぎわいに溢れる地域 へと昇華させるべく取り組んでまいります。
【地域の宝の育成】
深刻な少子高齢化を迎えているこの地域にとって、青少年は地域の宝です。地域のために 活躍する青少年を育成し、この地域の輝かしい未来を作り出していくことが私たちの責務で す。しかしながら、コロナ禍という現状において、青少年の心の育成が危ぶまれている状況 です。学校という、集団生活の中で人と交流しながら豊かな心を育んでいくべき場所におい て、人との交流を制限せねばならない状況が今もなお続いています。人と人との関わりの中 にこそ学びがあって感動があります。その関わりの機会自体が少なくなっている青少年たち の10年後、20年後の成長を考えたとき、どのような影響が出るのか計り知れません。
このような状況下において私たちが提供すべきは、甲府青年会議所のつながりを活かした 様々な人との交流の機会であると考えます。交流を通じてコロナ禍の鬱屈した心を解放し、 関係性構築を学び、その喜び、楽しさを感じてもらいたいのです。特に、ソーシャルネイテ ィブと称される世代のコミュニケーションはSNSを通じた一方的な情報発信とそのやりとりが主となりがちです。このような世代には、一緒に体験したり、意見交換をしたりする機会 を積極的に作り、協調性や共感力を養うことが必要です。
交流の機会としては様々なものが考えられます。青少年同士の交流や親子の交流はこれま でも多く取り組まれてきました。他にも、例えば異文化交流や国際交流なども子ども達の豊 かな心の育成に有益です。現在はSNSの利用により国内外問わず多くの情報を入手すること ができる時代です。しかし、自身が相手と対面し、生で情報交流を行う機会は、コロナ禍と いうこともあり限られています。私たち甲府青年会議所は、姉妹JCとしてのつながりや過去 の開催事業を通じてのつながりなど、活用できる独自の国際的ルートを持っています。これ らを活かして青少年達に交流の機会を作ることができれば、文化や歴史、価値観などの違い を学び、受け入れ、グローバルな視野を持った青少年を育成することにつながります。
また、世代を超えた人々との交流の機会も重要です。コロナ禍という閉鎖的な環境で、 「何もしたくなくなる」「無気力」な気持ちを抱える若者が増えています。そのような中 で、青少年と呼ばれる多感な時期に、家族以外の様々な大人と交流することは、自身の未来 を考える契機となり青少年の心に良い刺激をもたらします。特に私たちは毎年、地域に向け てまちづくり事業を展開しており、この活動に青少年達にも関わっていただく機会を作るこ とは有益であると考えます。青少年自身もこの地域の魅力を一緒になって考える機会になる とともに、地域のため、誰かのために本気で活動をしている大人と交流することは、自身が 成長し地域のために活躍する未来を考える契機にもなり、青少年の心をより豊かなものにす るでしょう。
【仕事と家庭とJCの好循環】
日々の生活にどれだけ満足できているでしょうか。スケジュールに忙殺される日々を送っ てはいないでしょうか。家庭をないがしろにしてはいないでしょうか。JC活動がなかなかで きないことを仕事や家庭のせいにしてはいないでしょうか。
近年、働き方改革や男女共同参画の推進により全国的にもワークライフバランスが注目さ れるようになりましたが、甲府青年会議所ではもっと以前から「仕事と家庭とJC」としてこ の3つの環境におけるバランスが話題にされることがありました。そして「仕事が」「家庭 が」ということを理由に青年会議所活動から離脱していく会員もこれまで少なからずいまし た。
青年会議所に入会するということは、「仕事と家庭」、「仕事とプライベート」という2 つの世界をさらに広げ、地域のため、誰かのために活動するという新しい自分を作ることで す。仕事と家庭の両立だけでも大変な中、それを押し広げてさらに「JC」という枠を作るの ですから、それまでの自分より多少の「無理」をしなければなりません。
しかし、この前向きな「無理」によって作られた「仕事と家庭とJC」という3つの世界の 好循環は会員の人生をより豊かなものにします。会員自身を大きく成長させるとともに、2 つの世界では生み出せなかったような大きな成果を生み出し、会員を新しいライフステージ へと導きます。
これは青年会議所に入会したら当然にもたらされるものではありません。それぞれの世界 に対する「感謝」という前向きな思いが必要です。「仕事」「家庭」「JC」のどの世界も諦 めず、大事にしながら活動をしたその先に得られるものです。できないことをどれかのせい にするのではなく、また、どれかをないがしろにするのでもなく、それぞれの環境があるこ とに感謝しながら両立をさせて活動したその先に、より良い好循環が生まれます。
そのために、両立をはかっていくための会員の取り組みや良い好循環が生まれた経験につ いての情報共有の機会や、いかにして両立をはかっていくか、両立のために組織に期待する ことなどについての意見交換の機会を積極的に作り出し、会員の育成に取り組んでいくこと が必要です。そして同時に、組織として、仕事と家庭とJCを結び付け、相互に理解を得られ るよう取り組みを行いながら、多種多様な会員の仕事と家庭とJCの両立を応援し、支えてい けるような持続可能な組織の構築へとつなげてまいります。
【JC活動への支援・協力】
私たちがJC活動を行っていくにあたって、青年会議所の成り立ちや、組織構成、役割、 ルール、出向とは何か、渉外とは何か、といった基礎的な知識は活動の基盤となる重要なも のです。特に近年アカデミー会員の活躍が目覚ましいこの組織においては、このような知識 を習得する機会を積極的に作っていく必要があります。
また、会内で理事を受けている会員の活躍は一緒に活動することで知ることができます が、出向先の会員の活躍はなかなか会内にフィードバックできていない現状があります。甲 府青年会議所からはほぼ毎年、役職者を輩出し、そこでの活躍は、本人に大きな成長の機会 をもたらしています。組織として積極的に出向者を輩出できるようにするとともに、輩出し た者をサポートしてその経験を会員にも還元できる機会を作るのが有益であると考えます。 そして、出向した会員の担当する渉外事業への参加を、LOM内においても積極的に促してい くことも必要です。ただ参加を呼びかけるだけではなく、どのようなメンバーが、どのよう な組織に出向し、どのような役目をもって活動しているのか、ということも、随時、メルマ ガや例会の機会を利用するなどして会員に周知すべきであると考えます。また、渉外に参加 するにあたっては、会員が訪れた先で最大限学び経験することができるように設えることが 求められます。
以上のように、2023年度は、個々の会員のJC活動を積極的に支援し、協力していく体制を 整えていきたいと考えています。
そして何より2023年は、私たち甲府青年会議所が山梨ブロック大会の主管LOMを務めま す。山梨ブロック協議会への出向者を支援するとともに、計画段階から連携を取り合って準 備を進め、ブロック大会の成功を甲府青年会議所の会員全員で支えていきます。
【組織の広報活動】
組織の広報を最大限発揮させるためには、広報を担当する委員会を運営ラインとして位置 づけ、この組織の活動全体の広報に専念させることが有益だと考えます。新聞・テレビ・ラ ジオ等のマスメディアへのアプローチ、ホームページやSNSを通じての発信等、ルーティン ワーク化できるものは行い、漏らさず、数多く、実施していくことがまず何よりも重要で す。その上で、ホームページやSNSの発信においては、発信内容・表現にそれぞれに応じた 工夫を行い、単なる一方的な情報発信ではなく、情報を受け取る側が興味を持ち、楽しみ、 共感できるような、個人の感性が入った情報発信を心掛けるのが望ましいと考えます。
これらを行うことを前提として、組織自体を広報しブランディングしていくような委員会 独自の事業をプラスアルファとして計画していくべきです。ステッカーやポスター等、過去 に作成したものを活用することも有益です。情報を繰り返し発信して人々に届けることで、 信頼感を高めていくことができるからです。
このようなきめ細やかな広報活動のもと、様々なメディアを駆使しながら、一方的な発信 ではなく情報を人々に届けることを繰り返し行いながら、この組織の魅力を伝播させ、組織 のブランディングへとつなげてまいります。
【会員拡大への取り組み】
上記のような広報を行いながら組織の認知度を上げていくこと自体が拡大にもつながって いきますが、それと同時に、やはり地道に声をかけ面談を行っていく手法は欠かせません。 会員の意識向上や会員からの情報の吸い上げを継続して行っていく必要があります。その際 には、会員拡大を担う組織が司令塔となり、理事長・理事三役も含めた会員全体で拡大に取 り組んでいくシステムの構築が必要です。また、拡大は、シニア会員の協力も不可欠です。 シニア会員との関係性を大事にし、これまで声を届けられていなかったシニア会員にも広く 協力を要請しながら活動を行っていくことが有効であると考えます。
さらに、外部向けの事業の機会を活用した拡大活動も行っていくべきです。事業・例会の 参加者や関係者、その他関わった人々は、甲府青年会議所の活動に何らかの点でマッチした 方々です。青少年事業に参加している子どもの保護者、フェイスペイントや湖衣姫の募集活 動で声をかけた地域の方々など、声をかけられる人はまだまだたくさんいます。拡大を担う 委員会には、他の委員会・例会等の機会を積極的に活用し、どんなときも拡大に専念しなが ら、機会を逃さず拡大活動に取り組んでいただきます。
そして最も大事に取り組んでいきたいことは、甲府青年会議所がどのような組織なのかを しっかり説明する時間を作り、会員として活動する楽しさや魅力をしっかりと伝えていくと いうことです。「入ってください」と依頼するのではなく「入りたいです」と言ってくれる 人を増やせるような前向きな拡大活動を展開してまいります。
【組織の基盤づくり】
以上のような運動を展開していくためには、より合理的でスリムな諸会議の運営が不可欠 であると考えます。特に、2023年度の理事構成メンバーには、従業員や母親といった、理事 役員としての活動が比較的困難と考えられてきた会員も少なからずいます。多様な会員の活 躍を推進するために、諸会議の開催時間やスケジュールの管理をしっかり行い、仕事と家庭 とJCを両立させられるよう、組織として体制を整えることが求められています。
組織としての会員の参加協力状況をみると、近年、例会や事業への出席率が低下している のが現状です。例会への出席は会員の義務であり、組織として由々しき事態であるととらえ ています。会員の例会離れの原因は多々あるかと思いますが、まずは、「例会は出席しなく てはならないもの」という意識を会員に持ってもらうための取り組みを行うべきであると考 えます。新たに入会してくる会員に対しては、入会の段階で意識付けを積極的に行っていく ことが必要です。現役会員に対しては、これまで行っていた取り組みをさらに強化させると ともに、意識を改められるよう、新しい取り組みを取り入れるなどして工夫をしていく必要 があります。例えば、理事長自らの呼びかけや、各例会における各会員への役割の割振り、 また、欠席理由書の提出、欠席が続く会員の理事会召喚等、様々な方法を模索すべきときで あると考えます。そして、このようにして大きな労力をかけて例会に会員を呼ぶ以上、例会 は充実したものとなるよう、理事として十分に内容を吟味し、計画していくことが重要です。
【総合計画の検証】
総合計画2021が施行され、今年で2年目の年となります。総合計画2021は、地域創生、会 員育成、組織発展の3つのビジョンを明確化し、「明るい豊かな社会」の実現を目指すべく 策定された5カ年計画です。私たち甲府青年会議所は、単年度制でありながらも、時代に即 した中長期計画に則り、「山の都共創宣言」の「夢ある未来を確信できる建都(まち)」の実現に向けた計画を実行し、引き継いでまいります。
【地域と連携した活動】
甲府青年会議所では、これまで地域と関わりながら様々な事業を展開してきました。地域 から継続を期待されている事業や、参加・協力を求められる事業等、地域からの信頼が形成 されてきた事業が多くあります。このような事業やその他地域に関わる諸事についても引き 続き組織として対応するとともに、地域で活動する他団体とも積極的に協力体制を築きなが ら精力的に活動してまいります。
【最後に】
新型コロナウイルスにより加速した社会の変化の渦中で、私たちは多くの制約の中ででき ることを探し、持続可能な地域をつくり次代につなげるためにできることを模索してきました。
しかし、私たちが見出さなければいけないのは、誰もが取り残されない社会、持続可能な 社会のその一歩先にあるのではないでしょうか。
甲府青年会議所が生まれた当時、社会は戦後復興の最中にありました。衣・食・住、様々 な環境が改善され、新たな技術、新たな経済活動が次々と生まれ、社会へと適用されていく 期待や希望があり、大きなエネルギーがありました。しかしながら、社会の成長が優先され、個々の尊重や権利に対する意識というものは今の価値感からすると発展途上であったの だろうと思います。
それから70年。技術の発展や社会の情報化は当時想像もつかないようなレベルで進み、も はやなくてはならないものとして私たちの生活を支えています。
一方、社会課題はどうでしょうか。解決したもの、改善したもの、依然として残っている もの、新たに生まれたもの、様々に混在しています。5年先、10年先、これらの課題はいっ たいどうなっているでしょうか。時の流れが、技術のさらなる革新が、または、どこかの誰 かが、解決してくれているのでしょうか。
時は人を待たず、ただ先へ先へと流れて行きます。
新たな価値観、変わり行く世界、めまぐるしく変わる時代の中であっても、私たちは自分 たちのすべきことを見据え、もっと先、もっと先へと歩みを進めていかなければなりませ ん。
夢ある未来を描き
時代に翻弄されず前進し
次代へ繋ぐバトンを持って、さあ、今を突き抜けて行きましょう。